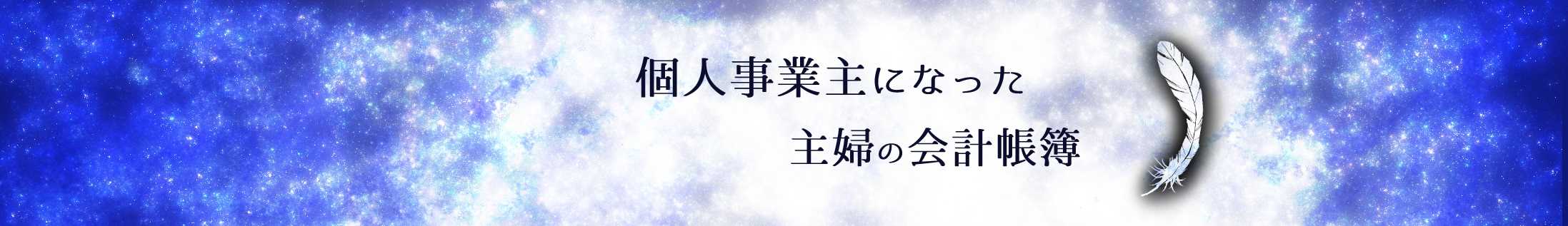「未払金」の似た科目として、決算勘定科目の「未払費用」があります。決算勘定科目は文字どおり、決算のときに使われる勘定科目です。
未払金と未払費用は、企業会計原則で区別するように明記されています。ただ、実務での処理は会社でのマイルールがあったり、給与の締め日によって未払金と未払費用の両方を使ったりすることもあります。
とはいえ、どちらの勘定科目を使ったらよいのか、と悩む方が多いのも事実です。実務では昨年度の仕訳を確認し、同じ処理を継続するようにしましょう。
目次
共通点が多く、仕訳に悩む勘定科目
どちらも貸借対照表の負債になり、決算日である12/31時点において、まだ支払っていない営業取引以外の費用をいいます。
未払金には二つのパターンがあります。ひとつは、支払期日が過ぎているにもかかわらず、まだ支払っていないもの。もうひとつは、支払期日がまだ来ていないけれど、債務が確定しているもの。
クレジットカード払いの場合、翌月以降の請求になります。請求が確定するのは、口座引き落とし日の二週間前というのがほとんどだと思います。つまり、12月末時点では、12月に発生した経費について「請求未確定」になっているはずです。
請求未確定ということは支払期日がまだ来ていない=請求書がまだ届いていない状態を指します。しかしながら、たとえ請求が未確定でも後日支払うことが確定している場合、費用として計上します。
したがって、12月に発生した経費のうち、1月に引き落としの費用は、未払金もしくは未払費用とするのが妥当です。
会計ルールは守らないといけない?
「企業会計原則」は税務上の拘束力はないものの、個人事業主を含むすべての人が規範とするべき会計ルールです。未払費用について、企業会計原則注解で下記のように記述があります。
注5 経過勘定項目について (損益計算書原則一のAの二項)
(3) 未払費用 未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対して、いまだその対価の支払が終らないものをいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過に伴いすでに当期の費用として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。また、未払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による未払金とは区別しなければならない。
未払金と未払費用は、分けて処理した方がよいということですね。ただし、これには例外があります。
注1 重要性の原則の適用について (一般原則二、四及び貸借対照表原則一)
(2) 前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについては、経過勘定項目として処理しないことができる。
重要性に乏しいというのは、当期の収益額への影響がない仕訳を指します。もっというと、金額が小さいもので、かつ、その勘定科目を使うことで経費が多くなり、所得が少なくならないもの。この条件に当てはまれば、未払費用の勘定科目を使わなくてもよい、ということです。
未払金と未払費用の違い
未払費用かどうかの見分け方として“継続したサービス(役務)の提供を受けたか”が判断基準になります。11月以前から契約をしており、かつ翌年1月以降も契約が継続するものについては、未払費用の可能性が高くなります。
もっとわかりやすくいうと、以下の3つの条件にすべて当てはまるのが「未払費用」です。未払費用にも買掛金にもならない未決済の費用は「未払金」で処理します。
- 継続性がある
- 支払期日が到来していない
- 商品の仕入れなどの営業取引ではない
電気代やインターネット代は、毎月継続して契約しているため未払費用です。反対に、備品などの消耗品は、その都度購入するものですので未払金になります。未払金と未払費用の違いを簡単にまとめると、以下のようになります。
| 未払金 | 未払費用 | |
| 継続性 | 単発 | 毎月発生(来期も継続) |
| 債務 | 確定 | 未確定 |
| 役務の提供 | 完了 | 一部完了 |
| 支払期日 | 過ぎている まだ来ていない | まだ来ていない |
未払金の例
- 新聞図書費
- 消耗品費
- 事務用品費
- 広告宣伝費
- 旅費交通費
未払金は後払いにした、毎月発生するとは限らない費用で、仕入れなど営業取引以外のもの。商品の仕入れの未払いは「買掛金」、内金や手付金は「前払金」です。
未払費用の例
- 水道光熱費
- 通信費
- 地代家賃
- 支払利息
- 給与
- 保険料
未払費用は毎月発生する費用で、継続したサービスかつ内容が変わらないもの。未払費用は、継続して支払っている経費が対象ですので、決算時に計上する金額は毎年同じ程度になるはずです。
期末の仕入れは未払金?買掛金?
商品の仕入れをした場合、未払いのものは「買掛金」で処理します。これは期末であっても買掛金のままで処理します。売掛金も同様です。
仕入れは、商売をするにあたって必要な作業ですよね。そして、仕入れが多いと、まとめて支払うために後払い(買掛金)というケースが多いと思います。
売上の収支を把握するのに、この買掛金という勘定科目は重要な科目です。仮に未払金で処理してしまったら、前年度の買掛金がいくらか、ということが分からなくなってしまいます。
したがって、買掛金は期末で未払いであっても、買掛金のままでOKです。翌期首に支払いが終わったときは買掛金で相殺します。未払金となるのは、消耗品費や広告宣伝費などの費用です。未払費用や買掛金は未払金にはなりません。
未決済項目と経過勘定科目
両者の違いは、継続性のある契約かどうかです。未払費用は「経過勘定科目」に含まれ、未払金は「未決済項目」に含まれます。通常、経過勘定科目は決算時にする仕訳で使います。
未払費用を計上する際は、他の勘定科目が発生していないかをチェックしておきましょう。ちなみに、前払費用は半年払い・年払いなど、来期ぶんも含めて一括で払ったときに使う勘定科目です。
| 未決済項目 | 経過勘定科目 | |
| 次期に繰り越す | 前払金、前受金 | 前払費用、前受収益 |
| 当期に含める | 未払金、未収金 | 未払費用、未収収益 |
| 継続性 | なし | あり |
期末の仕訳(決算整理)
| 日付 | 借方 | 貸方 | ||||
| 勘定科目 | 補助科目 | 金額 | 勘定科目 | 補助科目 | 金額 | |
| 12/31 | 水道光熱費 | 3,836 | 未払費用 | freeeカード | 3,836 | |
| 12/31 | 通信費 | 1,600 | 未払費用 | freeeカード | 1,600 | |
| 12/31 | 事務用品費 | 916 | 未払金 | freeeカード | 916 | |
| 12/31 | 新聞図書費 | 1,200 | 未払金 | freeeカード | 1,200 | |
| 12/31 | 消耗品費 | 5,616 | 未払金 | freeeカード | 5,616 | |
決算整理なので、日付は12月31日で計上します。借方は経費の勘定科目、貸方は未払金or未払費用とします。
未払金や未払費用の補助科目に「●●カード」や「●●銀行」と引き落とし予定のカード名や口座名を入力しておくと、「あれ?なんの未払金(未払費用)だっけ?」と頭を悩ませる必要がなくなります。来期にする勘定科目の相殺仕訳もしやすいです。
期首の仕訳(翌年)
| 日付 | 借方 | 貸方 | ||||
| 勘定科目 | 補助科目 | 金額 | 勘定科目 | 補助科目 | 金額 | |
| 1/27 | 未払金 | freeeカード | 7,732 | 事業主借 | 7,732 | |
| 1/27 | 未払費用 | freeeカード | 5,436 | 事業主借 | 5,436 | |
クレジットカード払いの場合、引き落としが完了したら、前期の未払金や未払費用を相殺します。日付は引き落とし日でOKです。金額は、決算時にそれぞれの科目に計上した合計額になります。念のため、請求書の金額と引き落とし予定額が合っているか、確認しておきましょう。
最後に、残高試算表にある未払金や未払費用の期末残高がゼロになっていたらOKです。仮に違っていたら、どこかで数字の入力を間違えているのかもしれません。
本来の勘定科目と異なる処理をした場合は?
仮に未払費用とするべきところを未払金としていても、税務上はさほど問題はありません。税務署がチェックするポイントは、売上の計上もれや不正な経費の計上など、脱税の疑惑があるかどうか、です。
未払金と未払費用の勘定科目を振り替えただけでは、納税額は変わりません。税務調査は追徴が主な目的ですので、経費の勘定科目が多少違う程度では、税務署から目をつけられる可能性は低いでしょう。
次回は「前払費用」について解説します。
-

-
決算整理仕訳その2「前払費用を計上しよう」
「前払金」の似た科目として、「前払費用」があります。前払金が商品引き渡し前に代金を前もって渡すことであるのに対し、前払費用は来期以降の費用を先に支払った場合に使います。 まだ利用していない期間の費用、 ...